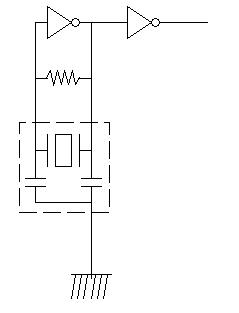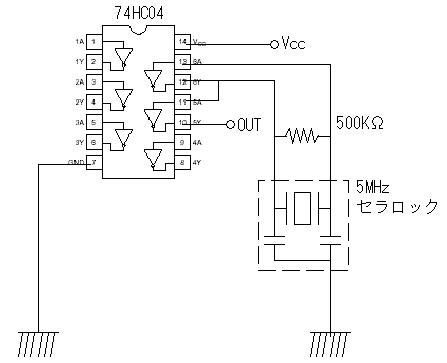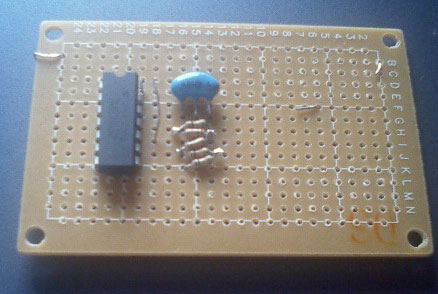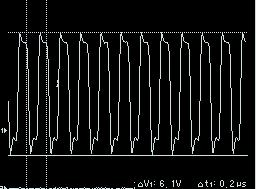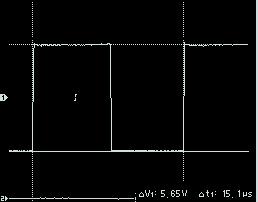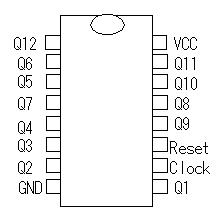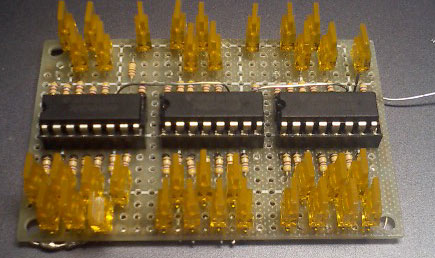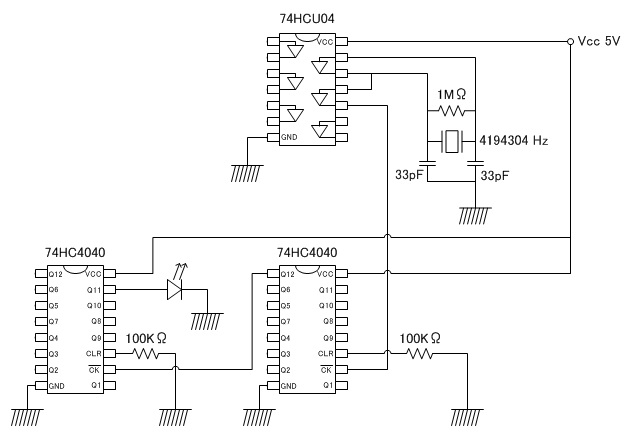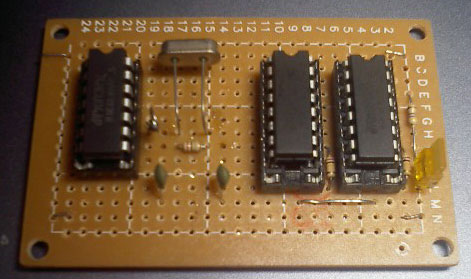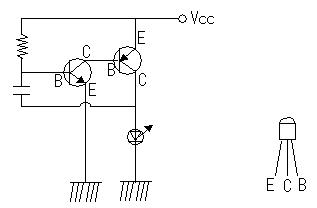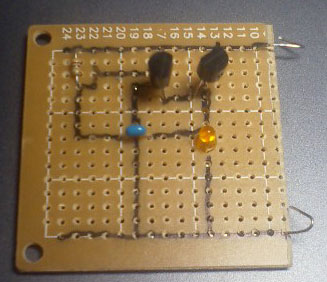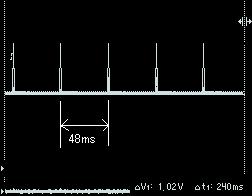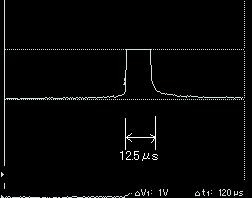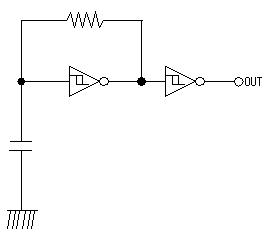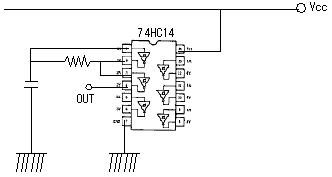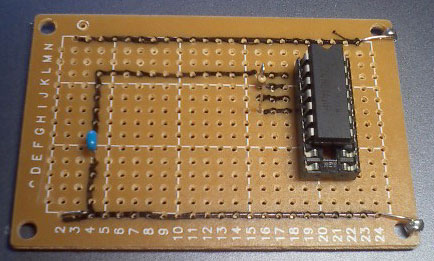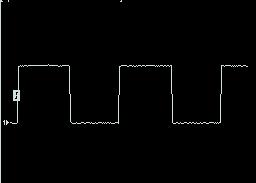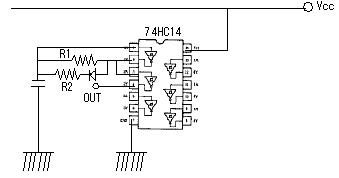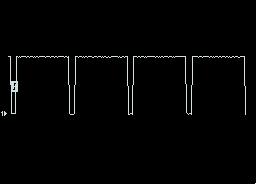■発振する回路を作ってみる
デジタル機器でよく使われるという発振回路
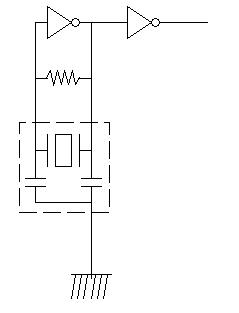
ちょうど、手元にあった5MHzのセラロックと、74HC04と抵抗100KΩ5本を使って作ってみます。
本来なら異常発振するらしいから2段バッファの74HC04を使うべきでないらしいです。
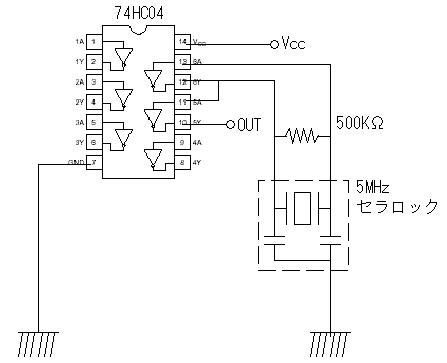
実際に作成した基盤
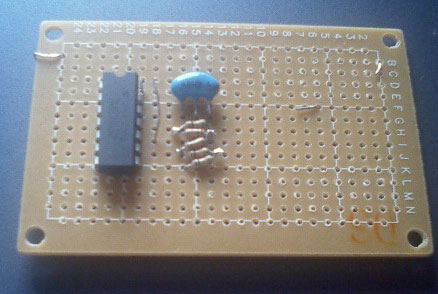
発信波形をオシロで見てみると
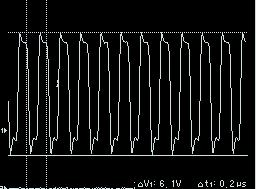
一つの波形が0.2μs = 0.0000002秒ですから5MHzで発振しています
次に、セラロックをクオーツ時計から取り出した、65536Hzの水晶に取替え、
コンデンサを33PFの物を取り付けました
電源を入れると、高い周波数での発振が起きました
周波数が緩やかですから、チャタリングと同じ現象が起きてると思い
NOTをシュミットトリガ 74HC14 に変更し測定してみると
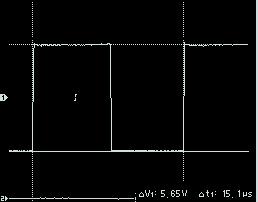
一つの波形が15.1μsで発振しています
計算上では
1秒 / 65536Hz = 0.00001525・・・・ つまり15.25μs
近い値です。
うまく発振してるみたいです。
■一秒おきに ON/OFF できるようにする
一秒おきに ON/OFF できるようにするには、周波数をカウントする必要があります
そこで登場するのが、カウンタ。
中にフリップフロップが沢山ならんでいて、Clockを入力すると2進数でカウントしてくれます
74HC4040 ちなみに名古屋の大須で購入
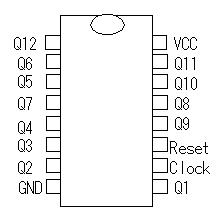
Q12をResetに接続すると、複数のカウンタを連結できるのでいきなり3つ連結してみました
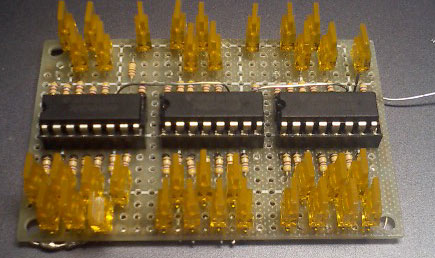
動作確認をするとまったく動作しませんでした。
原因はResetをGNDに繋いでいなかったためでした。
端子は宙ぶらりん厳禁ですねえ、とりあえず100KΩの抵抗を取り付けてGNDと接続しました。
一段目の Clock に ON/OFF を入力すると、信号の立下りでカウントされていくことが確認できました。
上で作った65536Hzの発信回路を接続してみると。
だいたい1秒ぐらいの時間で、17bit目が点滅しました。
▼1秒をカウントする
4194304Hzの水晶を大須のタケイ無線で購入
4194304 は 二進数で 0100 0000 0000 0000 0000 0000
22bit目がON/OFFする時が1秒となります
23bit目だとONで1秒、OFFで1秒の0.5Hzになります。
回路図的にはこんな感じです NOT回路をアンバッファタイプに変更しました
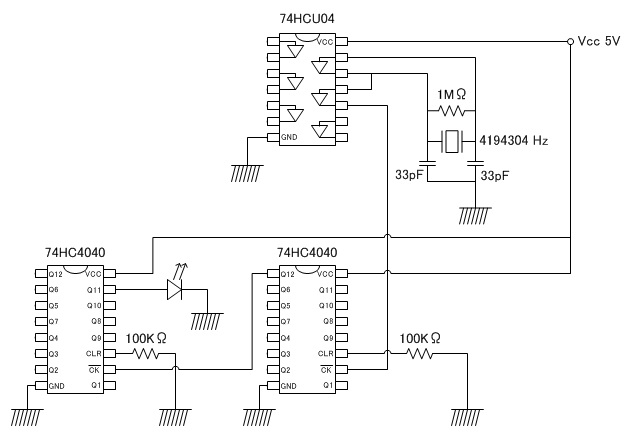
Q11だと、0.5Hzが出力されますので一秒毎にLEDが点いたり消えたりします。
1Hzを取り出そうとするとQ10でしょうか。
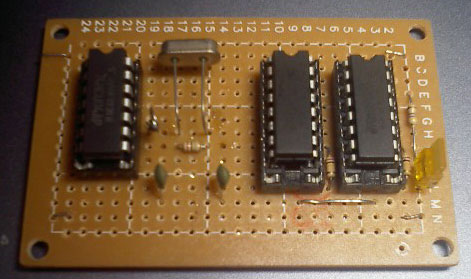
■電子ブザーなどに使われる回路
本来はスピーカの着く所にLEDを付けました
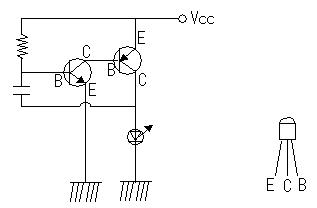
トランジスタに2SC1815と2SA1015
抵抗に1MΩ
コンデンサに0.1μFを使いました
コンデンサの値を大きくするとゆっくり点滅します
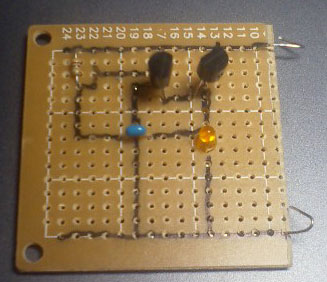
出力波形をオシロで見ると
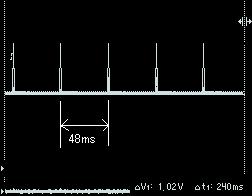
拡大
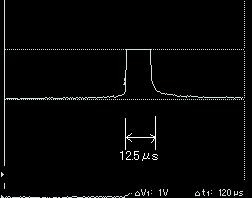
尖がってるところがLEDの点灯箇所
ほんの一瞬の間だけLEDが点灯してるのが判ります
■論理回路を使ったCR発振
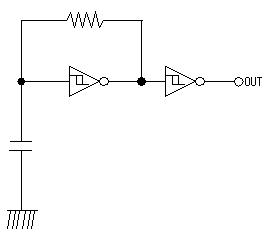
回路図的にはこんな感じです
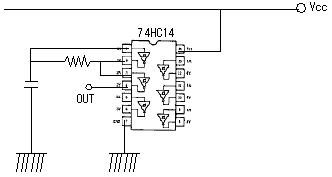
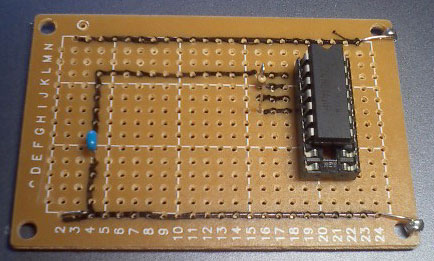
出力波形をオシロで見ると
HとLが対称に出力されています
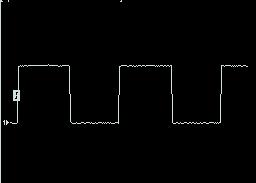
▼波形のLの時間を短くする
R1の抵抗より小さな抵抗R2とダイオードを取り付けました
これにより、HとLでの抵抗値が切り替わり、出力波形が変化します
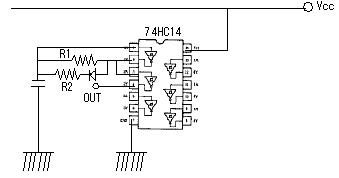
波形をオシロで見ると
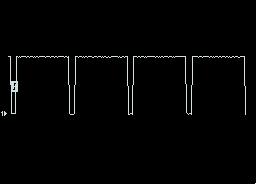
Lの時間が短くなっているのが判ります。
▲トップページ
>
マイコンなど